2025.02.14
2月室内装飾「節分」

節分は「立春」の前日にあたります。立春は暦の上で春が始まる季節のこと。つまり、節分は冬の終わりの日で、翌日から新しい季節が始まる区切りの日となります。そのため、邪気や悪いものを落として、新しい年に幸運を呼び込むことを目的に、節分という行事が日本各地で行われてきました。
・豆
鬼は邪気や厄の象徴とされ、形の見えない災害、病、飢饉など、人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられてきました。鬼を追い払う豆は、五穀の中でも穀霊が宿るといわれる大豆です。豆が「魔を滅する(魔滅)」、豆を煎ることで「魔の目を射る」ことに通じるため煎った大豆を使い、これを「福豆」といいます。
・ヒイラギ
鬼は、鰯(いわし)の生臭い臭いと、柊(ひいらぎ)の痛いトゲが大の苦手とされています。そこで、鰯の頭を焼いて臭いを強くしたものを柊の枝に刺し、それを玄関先にとりつけて、鬼が入ってこないようにする風習があります。これを「焼嗅(やいかがし)」「ヒイラギ鰯」などと呼びます。
各クラスの様子をお伝えしたいと思います。
<ほし組>
「ヒイラギはチクチクしているね」と声を掛けるとおそるおそる手をのばして触れてみようとするほし組さん。ヒイラギを手に持ち振ってみると、床に当たった時の”カサカサ”という音に気が付いて繰り返し叩いて音を楽しんでいました。動かしていると葉っぱが取れ、”これは何だろう”といった表情で観察する姿もみられましたよ。
豆は誤飲を防ぐために袋に入れて観察をしました。床に落としてみた時の面白い音に保育者の顔を見て「へへっ」と笑って気づきを共有したり、手で握って感触を確かめたり、近くにあったコップを手に取り中入れてみたり…五感を使って親しんでいました。






<つき組>
ヒイラギを勢いよく触るとチクチクした感触に険しい表情を浮かべていました。「ちくちくが痛かったね」と応答すると「これ痛いよー」と、びっくりしたのかそのあとは触らず、豆の方に興味を示していました。
豆の皮が剥けることに気付くと一粒一粒集中して剥いていました。時折豆が割れることに気付いた子も。「あ!」と何か思いついたようにつぶやいた子は、豆を置くと手のひらで上から圧力をかけて割っていました。「押しつぶすと簡単に割れたね!」と保育者が気づきに共感すると、少し得意げな顔をして次々と押しつぶしていました。また、硬い豆は割れず、「なーい」とできないことを伝える子もいました。割れなかった豆はヒイラギについていた豆のさやからでてきた豆でした。同じ豆でも硬さや形の違いに不思議そうに見比べていました。
皮を剥いたり割るだけではなく、においを嗅ぐ姿もありましたよ。


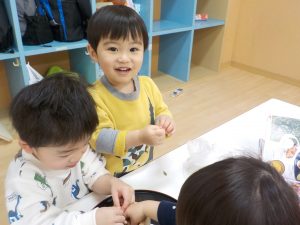

<そら組>
「節分は何したの?」「パパが鬼になって豆まきした」との声もありました。
そら組さんの観察する順番が回ってくると”やっとそら組の番だ”と期待いっぱいで取り組み始めました。
「鬼はヒイラギが苦手なんだって」とお話しすると鬼にヒイラギを向けて鬼退治する子、鬼に豆を食べさせようとする子がいました。「豆がやわらかくなるんだ~」と炊飯器に入れて料理をしたりヒイラギをほうきに見立てて掃除をする姿もありましたよ。
そら組さんは家で体験したことを思い出しながら観察したり、物の性質や仕組み、用途などを理解しながら遊びに発展している印象でした。




<給食、おやつ>
2月3日は行事食で恵方巻、鶏照り焼き、けんちん汁、おやつではきな粉大豆、いちごを食べました。
そら組では給食の前に節分について一緒に調べてみました。「恵方巻を食べるといいことがあるんだって~」の保育者の言葉に「なんで?」と疑問に感じる子どもたちでした。日々過ごしていく中で、行事や季節ならではの物に触れられる機会を作っていきたいと思っています。









