2025.05.09
【つき組】戸外遊び・5月の室内装飾〈端午の節句〉
今週はつき組の戸外遊びについてお届けしたいと思います。
慣らし保育の2週間目、園生活に慣れてきたころにお散歩に行きはじめました。初めての散歩は園周辺を一周して風を感じたり、音を聞いたり、植物など発見して戸外活動を楽しんでいました。


園の外に出ることや手を繋いで歩くこと、散歩車に乗ることに戸惑う様子もありましたが、公園では保育者と一緒に花や虫など自然物の発見を楽しんだり、電車や車など乗り物を見たりしながらやり取りを楽しむうちに心地よさや楽しさを味わう様子が見られるようになってきました。園周辺のお散歩を通して外で遊ぶ事への興味や期待が広がってきているように感じます。


戸外活動中は心地よい気候の中タンポポや綿毛に触れてみたり、アリを見つけ観察したりと興味津々です。感触をじっくり手で確かめる子や色や形を見て観察する子など探索の様子も様々です。



身体を動かすことも活発で緩やかな坂の上り下りや「まてまて」と保育者との追いかけっこも楽しんでいます。十分に満たされていく中で普段一緒に過ごしているお友達にも保育者を通して興味を持ち、お友達とのやり取りが散歩中にも見られるようになりました。離れたところにいるお友達に手を振ってみたり、木の陰から「ばぁ!」と顔を出して笑い合ったりと公園に行く度に楽しさを共有している様子です。

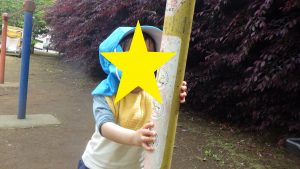

今後も暖かさが心地よい季節に自然に触れながら戸外活動を楽しんでいきたいと思います。
5月の装飾のテーマは【端午の節句】です。

端午の節句とは、五節句のひとつです。古代中国では、古くから季節の代わり目の5月になると薬草である菖蒲酒を飲み、菖蒲を腰を下げるなどして、体の汚れをはらう厄除けの行事をしていました。
端午の節句に柏餅を食べる風習は、江戸時代に日本で生まれました。柏の葉は、新しい芽が出るまで落ちない、というところから、“子孫繁栄”の縁起を担ぐとされています。神事に欠かせない餅を縁起の良い柏の葉で包んだ柏餅を端午の節句に食べることにより、男の子が元気に育つことを願っています。柏餅を食べる風習は関東を中心に東日本へ広がりました。また、「鯉」というお魚は、強くて流れが速くて強い川でも元気に泳ぎ、滝をものぼってしまう魚です。そんなたくましい鯉のように、子どもたちが元気に大きくなることをお願いする意味が込められています。五色の吹流しは、子どもの無事な成長を願って悪いものを追い払う意味が込められているそうです。今も昔も、子どもを大切に思い成長を願う気持ちが込められています。
そんな季節にぴったりな柏餅と折り紙で作ったこいのぼりと兜を玄関に飾ってみました。子ども達もお餅に興味津々で散歩に行く際に玄関に行くと「お餅だねぇ」と保育者にお餅が見えた事を教えてくれる姿がありましたよ。長期休み中にこいのぼりを実際にみた子どもは折り紙のこいのぼりをみて「こいのぼりみたの」実際の経験を言葉で伝えてくれる子どももいました。
こどもの日の由来など知っていく中で、私たち保育者も子ども達の健やかな成長を願い大切に1日1日を過ごしていきたいと改めて感じています。

